前に、「短調が3種類ある」という記事を書きました。
そのときに、「Ⅴ(5の和音)」や「Ⅰ(1の和音)」をどうしても記載せざるを得ない
場面がありました。
短調を理解するうえで、どうしてもローマ数字で表す、和音の性格”や“役割”の話を避けて通れないと感じたからです。
そこで今回は、その記事の前段階の知識として、
「なぜポップスではCやAmと書かれ、クラシックではⅠやⅤ7のローマ字数字で書かれるのか?」
というテーマで書いてみようと思います。
私の音楽理論の説明は、音楽を専門にしていない方──
たとえば職場の同僚に話すようなイメージで書いています
できるだけ難しくせず、ふだんの言葉でやわらかくまとめています。
音楽理論には、さまざまな説明や本があります。
もし読んでいて「ここ気になるな」「もう少し知りたいな」と思ったら、
どうぞ自由に調べてみてください。
その小さな興味が、学びを広げてくれる大事な一歩になります。
このブログが、そのきっかけのひとつになれたら、とても嬉しいです😃
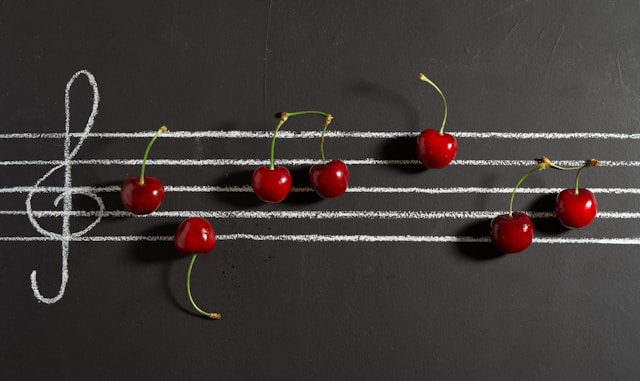
例えば、楽譜でこんな表記を見たことはありますよね。
🎵 C Am F G7
これはポップスなどでよく見るコード(和音)の名前です。
でも一方で、クラシックや音楽理論の本を開くと——
🎵 Ⅰ Ⅵ Ⅳ Ⅴ7
と、ローマ数字が並んでいます。
「どっちも同じ音楽なのに、なんで書き方が違うの?」
と戸惑ってしまう事があるのでは・・と思います。
① コード(CとかAm)=「音の名前」
まず、C や Am は「実際に鳴らす音の名前」です。
たとえばピアノで「ド・ミ・ソ」を押すと、それが C(シー) です。
「ラ・ド・ミ」を押すと Am(エーマイナー) です。
つまり、今どの音を弾くかを教えてくれるのがこの書き方。
ギターやピアノ(特に伴奏)を弾く人には、とっても便利です。
② ローマ数字(ⅠとかⅤ)=「場所の名前」
一方で、クラシックのほうに出てくるローマ数字は、
“ドレミファソラシ” の中の「何番目の音を中心にした和音か」を表しています。
たとえば、ドレミファソラシのドを「1番目」としたとき:
| 和音の中心 | 音の並び | ローマ数字 | 意味 |
|---|---|---|---|
| ド | ド・ミ・ソ | Ⅰ | 1番目の和音 |
| レ | レ・ファ・ラ | Ⅱ | 2番目の和音 |
| ミ | ミ・ソ・シ | Ⅲ | 3番目の和音 |
……というように、番号で場所を表しているんですね
だから、「C」と書かれていても、その曲がCメジャー(ハ長調)か、
Gメジャー(ト長調)かによって、その和音の役割は変わります。
なぜなら、Cはドミソなので、Cメジャー(ハ長調)だったら、
Ⅰの和音だけど、Gメジャー(ト長調)だったら、Ⅳの和音になるからです。
(ソから始まって、ドは4番の音。)
③ そして、ローマ数字は「役割」を見るためのもの
そして音楽には、「落ち着く」「出発する」「緊張して戻りたくなる」といった流れがあります。
たとえば:
- 家に帰ってきたようにホッとする → トニック(Ⅰの和音)
- 少し遠くに行く → サブドミナント(Ⅳの和音)
- そろそろ帰りたくなる → ドミナント(Ⅴの和音)
ローマ数字で見ると、曲の中で「どんな役割をしているか」が分かる。
ポップス「C」や「Am」のようなコード表記だけでは“音”は分かっても、
“役割”までは分かりません。
クラシックではそれを見えるようにしているのです。
他の和音の役割を下記の通りまとめました。
| 名前 | 英語 | 記号 | 感じ方 |
|---|---|---|---|
| トニック | Tonic | Ⅰ、Ⅵ | 落ち着く・帰ってきた感じ |
| サブドミナント | Subdominant | Ⅱ、Ⅳ | 広がる・出発する感じ |
| ドミナント | Dominant | Ⅴ、Ⅶ° | 緊張・戻りたくなる感じ |
④ じゃあ、どっちがいいの・・?
どっちも良くて、どっちも、使われています。
ざっと、簡単ですが下記にまとめてみました。
| 使い方 | 目的 | 表記例 |
|---|---|---|
| ポップス・バンド | 今すぐ弾く音を伝える | C, Am, F, G7 |
| クラシック・理論 | 曲の中での「役割」を見る | Ⅰ, Ⅵ, Ⅳ, Ⅴ7 |
たとえば、ポップス、ジャズの即興なんかではコードを言う事で
「今日はこのコードで即興演奏しよう!」とすぐに音を出せることができますよね。
一方、ローマ字数字が使われてクラシックでは
「この曲はなぜこの和音進行で美しく聞こえるのか」を考えることができます。
つまり、実際に弾くための言葉と、曲を考えるための言葉があって目的によって
使われるんですね。
まとめ
| 見方 | 教えてくれること | 使われる場面 |
|---|---|---|
| C, Am, G7(コード) | 今、何の音を弾くか | ポップス、バンド、伴奏など |
| Ⅰ, Ⅳ, Ⅴ7(ローマ数字) | 曲の中での位置や役割 | クラシック、分析、作曲など |
💡私の感想
今回改めてこの記事を書いてみて、
「音の書き方ひとつにも、考え方の文化があるんだな」と感じました。
私は今、クラシックの和声(機能和声)の勉強をしているのですが、
ローマ数字で音楽を見ると、常に「この和音はどの調の中で、どんな役割をしているのか」
を意識させられます。
たとえば、Ⅴがドミナントとしてどう機能しているか、
Ⅰにどう解決しているかなど、音の流れを“構造”として捉える感覚が自然に身についていきます。
ポップスのコード表記が「その瞬間の音」を教えてくれるのに対して、
クラシックのローマ数字は「音の関係と流れ」を見せてくれる。
簡単なことではないですが、その両方を理解すると、
音楽の感じ方がより立体的になると感じました。
🎶 最後に:機能和声のことを少し
機能和声という言葉が出たのでちょっとそれについて触れてみたいと思います。
この記事では、「トニック」や「ドミナント」という言葉が出てきました。
そして、ローマ数字は「役割」を見るためのものでしたよね。
この役割すなわち、“和音の性格”や“流れ方”を研究したのが、
機能和声(きのうわせい)という考え方です。
音楽を「なぜそう聞こえるのか」という視点で見る考え方で、
曲の中の「落ち着く → 動く → 緊張 → 落ち着く」という心地よい流れの中に、
音楽らしさを感じる仕組みを見つけること(学問)です。
ちょっと、難しく聞こえがちですが、私たちの耳が自然に感じていることを、
理論として言葉にしたものとも言えます。
機能和声を学ぶと、音の流れの意味が見えるようになります。
なぜここで落ち着くのか」「どうしてこの和音が使われているのか」――
その理由がわかると、音楽がもっと面白く、深く感じられます。
少しだけその“流れ”があることを意識して弾いたり、聴いてみたりしてみてください。
きっと、いつもの音が少し違って感じられると思います。

