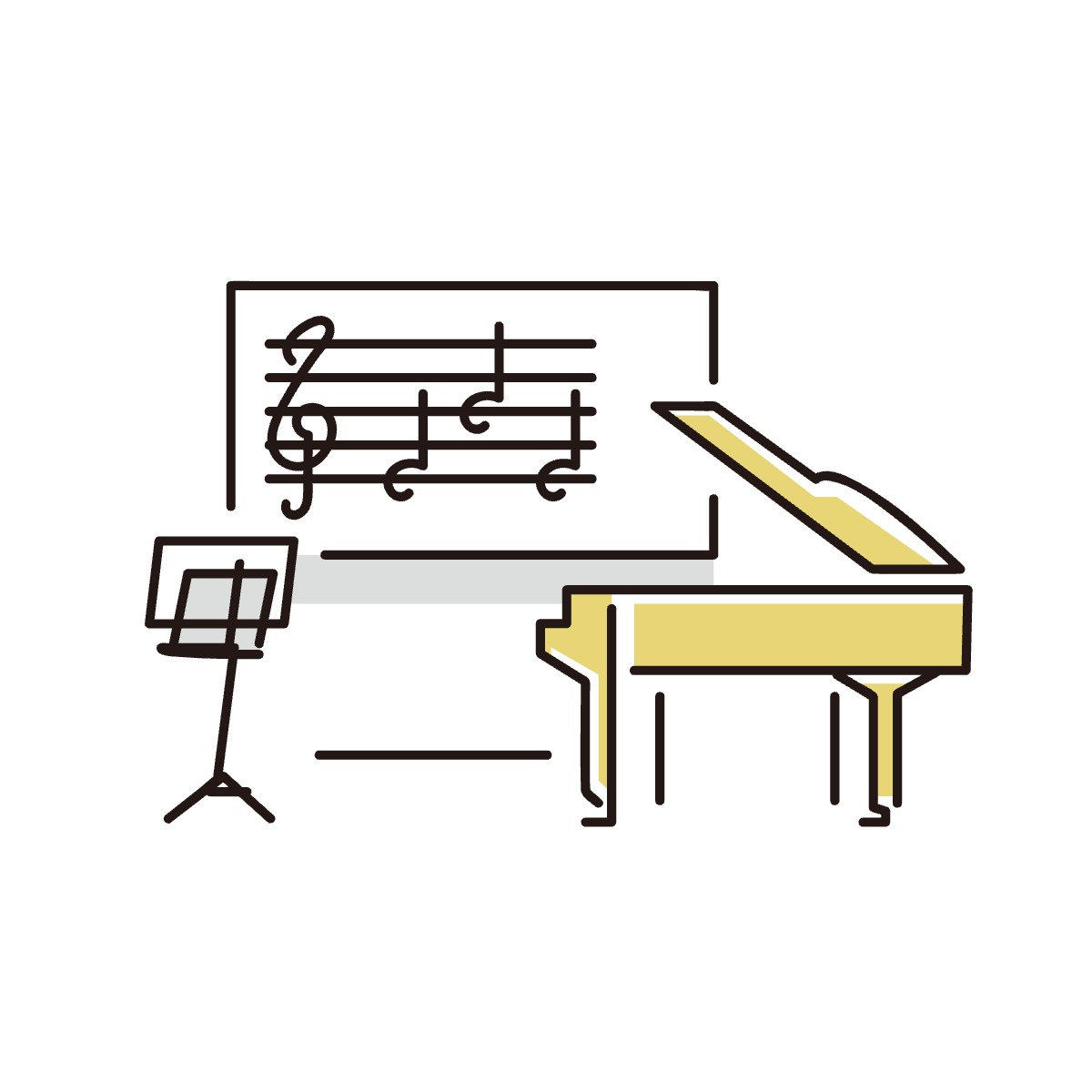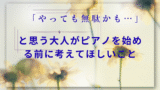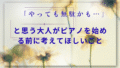― 私とバッハと、日々のなかで ―
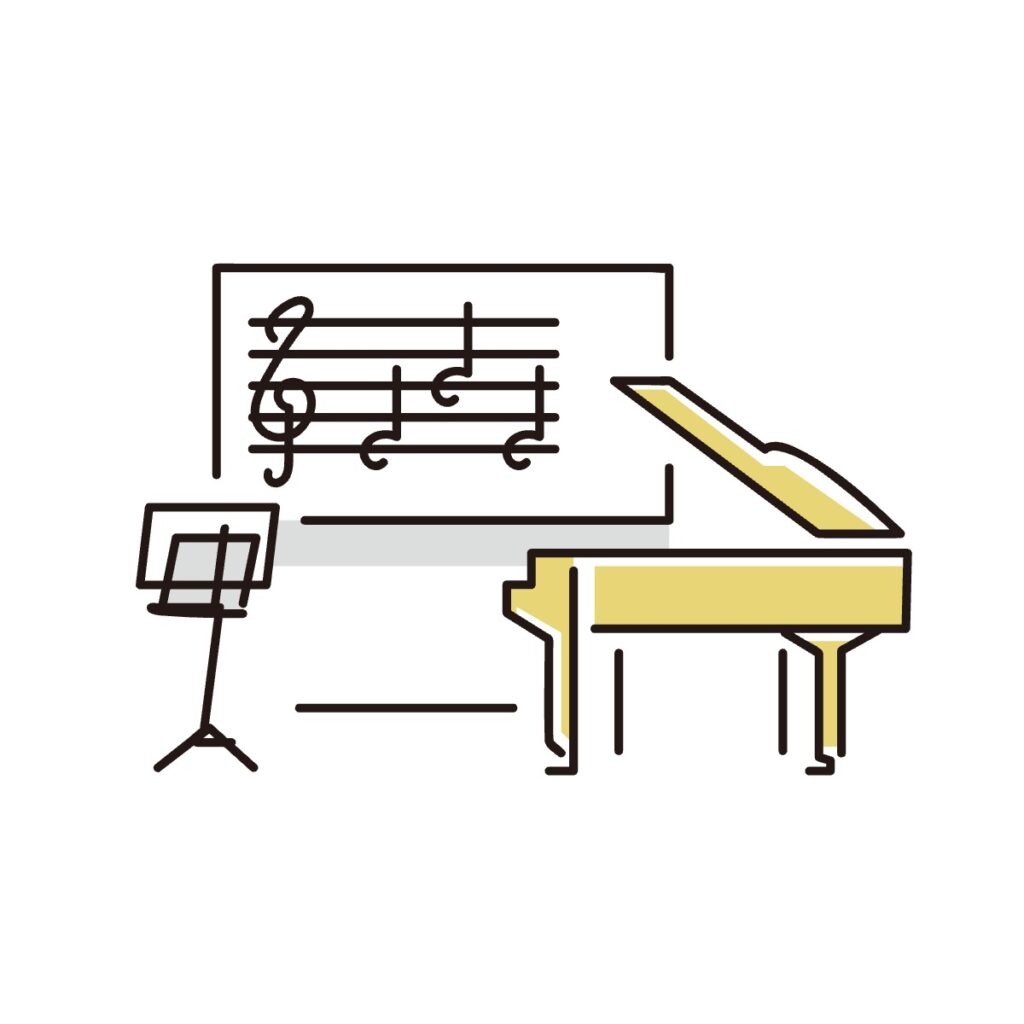
今までブログを書いてきて、私なりに思ったことを少し書いてみたいと思います。
私がブログを始めたきっかけというのは、一般の会社で働いている一人として、職場の仲間たちから音楽のことについていろいろ聞かれたり、話題にしてもらったりする中で、
「ああ、こんなにも音楽と一緒に生活したいと思っている人が世の中には多いんだな」
と感じたことでした。
私は小さい頃からピアノをやってきたので、音楽が生活の中にあるのが自然だったのですが、
そうではない環境で育った人の中にも、
音楽を日々の暮らしに取り入れたいと思っている方が
本当に多いんだなと気づきました。
でも一方で、時間がなかったり、「自分には無理かも」
といった心理的なブロックを感じている人も多いように思います。
そういう人に寄り添うような、そして少しでも役に立つようなブログが
あったらいいなと思いました。
いわゆる、そういったことを書くのは、
私のように両方の立場がわかる人間だからこそ書ける
部分もあるかもしれないと思いました。
私はいくつかの記事でも書きましたが、
少しの間イギリスに留学していたことがあります。
そのとき、現地で音楽のレッスンを受けていたこともありました。
もちろんこれは一つの個人的な経験に過ぎないのですが、
あちらで生活していて感じたのは、「音楽に対する向き合い方の空気が違う」ということでした。
うまくは言えませんが、イギリスでは、たとえば教会などでも、
それこそ老若男女の人々が自然に歌っていて、
歌うということが日常に根づいているように感じました。
そこには、「うまく歌えるかどうか」とかの考えは全く存在せず、
もっと人間の日常の営みに近い感覚でに音楽と関わっている姿があって、
私はこういった感覚はすごいなと感じました。
もちろん、これは海外がすばらしい、日本があんまり・・、という話ではありません。
ただ、音楽が人間の一つの営みとして生活の中に自然にある、
そういう風景に触れたときに、「上手いとかは重要ではない」
と素直に思えるようになった気がします。
なので、「ちょっとピアノとか音楽を楽しみたいけれど、
なんとなくプレッシャーを感じてしまっている」という方がいたら、
無理にがんばろうとしすぎず、自分の営みの一つとして考え、“等身大”の感覚を
取り入れてみてもいいんじゃないかなと思います。
上手くなくてもいい、自分のタイミングで、自分の音楽と向き合う。
それだけで、十分に素敵なことだと思うんです。
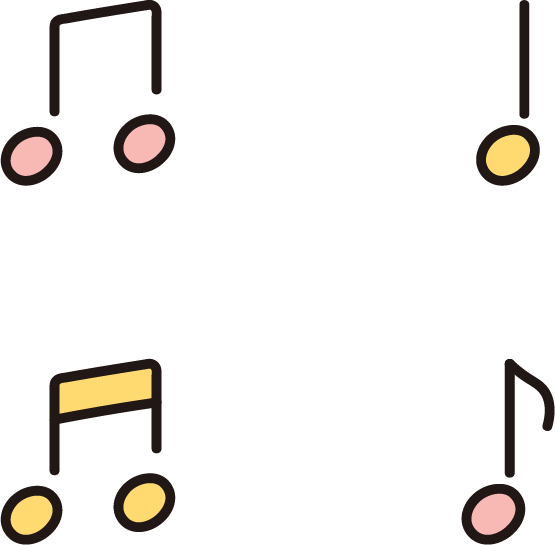
私は小さい頃からクラシックピアノのレッスンを受けてきました。
ブルグミュラー、チェルニー30・40、ソナチネ、ソナタ、バッハ…。
今にして思えば、少し昔ながらのやり方かなと思います。
その中で、「得意な曲」「不得意な曲」も当然ありました。
でも、私はずっとバッハを弾くのは好きでした。
でも、すごくうまく弾けるというわけではありませんし、
また私は、それなりに練習しないとできないタイプです。
だけど、バッハの音楽にはどこか波長が合うような、
言葉にならない感覚があります。
たとえば、初めて行った場所なのに、
なぜか懐かしく感じるようなことってあると思います。
私にとってのバッハは、そんな存在です。
特別であり、懐かしくもある。
「上手に弾けるか」ではなく、「自然にそこにいたいと思えるような音楽」。
弾いていても、聴いていても、
バッハの宇宙の中に静かに存在しているような、
そんな安心感があります。
練習しないとできないのはもちろんですが、
それでも「ここに戻ってきたい」と思える音楽。
それが、私にとってのバッハです。
また、忙しい日常の中でなんとかやりくりして、
ピアノを弾いたり、音楽に向き合ったりする。
その一つ一つの行動こそが、すごく素晴らしいことなのではないかと思います。
生きているだけで、いろんな情報や意見が次々と入ってくる世の中ですが、
どうか、自分なりのペースで、自分なりの正解を、
少しずつ見つけていっていただきたいと思います。
自分の感覚で、音楽を語れたり、聞けることができたらそれは、
かけがえのないものなんだと思います。
おわりに(読んでくださったあなたへ)
このブログが、音楽に対してちょっと距離を感じていたり、
プレッシャーを感じている誰かの、
ほんの少しの安心やきっかけになったら嬉しいです。
自分だけの音楽との付き合い方、自分だけの“好き”を、
どうか大切にしてみてくださいね。